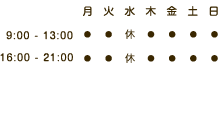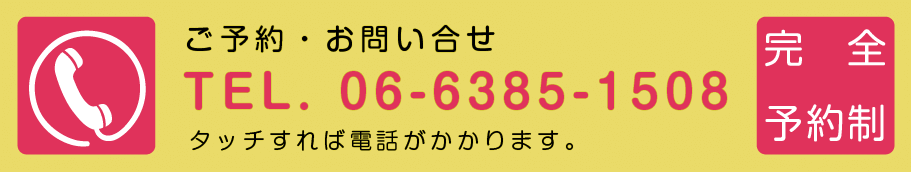BLOGカテゴリー
頭痛
国民の3人に1人が悩んでいる頭痛。西洋医学的な観点はもちろんのこと、統合医療・東洋医学の面から見た頭痛の原因や対処法をお伝えします。「もう治らない」「諦めた」そんな方は必見の内容です。
この記事の目次
このような症状でお悩みではありませんか?

☑頭が締めつけられるような感じがする
☑目の奥が痛い
☑時々頭がズキズキする
☑常に頭がズーンと重くスッキリしない
☑首から後頭部にかけて固まっている感じ
☑こめかみ付近が痛む
☑上あごに違和感がある
☑鎮痛剤が手放せない
「あ、頭が。。。」
上記の様な症状でお悩みのあなた。
その症状でいつから悩まされていますか?
医療機関へは行かれましたか?
きちんと原因は分かりましたか?
現在の日本では、慢性頭痛に悩む方の割合が35~40%とも言われています。
実に国民の3人に1人以上の方が頭痛(しかも長年)に悩んでいることになります。
今回はそんな頭痛についてのお話です。
頭痛の種類や原因はもちろんのこと、東洋医学や統合医療の立場からみた頭痛(←※これ、重要です)についても解説していきます。
「色々調べたけど、もうあきらめている」
そんなあなた、是非ご一読下さい。
さて、まずは頭痛の基本的なお話から。
頭痛の種類
一口に頭痛と言ってもその種類は様々あります。
まずは、大きく3つに分類しましょう。
①一次性頭痛(機能性頭痛)
いわゆる”頭痛持ち”の方の慢性頭痛のことです。
頭痛に悩む方全体の80%はこの頭痛に属すると言われています。この頭痛の中に、「緊張型頭痛」「偏頭痛」「群発性頭痛」の3つがあります。
今回は、皆さんからのお悩みが特に多いこちらの頭痛を中心に解説していきます。
各頭痛の特徴については、次のテーマで取り上げたいと思います。
②二次性頭痛(症候性頭痛)

病気や外傷によって起こる頭痛のことです。
例えば、くも膜下出血、脳腫瘍、脳血管障害などによって起こる、命にも関わるものです。
この頭痛を抱えた状態で整体や鍼灸に来られるケースはほとんどないとは思いますが、ただちに専門医を受診する必要があります。
③風邪や二日酔いでの頭痛
上記で起こるような日常的に起こる頭痛のことです。
ほとんどの場合、風邪や二日酔いがなくなることで自然と治っていくもの。
一次性頭痛の種類
先ほどお伝えしました一次性頭痛(緊張型頭痛、偏頭痛、群発性頭痛)についてそれぞれ解説していきます。
①緊張型頭痛
緊張型頭痛は、頭の周りを何かで締めつけられるような鈍い痛みが出ます。
個人差はありますが、数分程度の短時間なものから、毎日続くようなケースまで様々です。
感覚的には「はちまきをギュッと絞めたような」「ヘルメットをかぶったような」といった感じでしょうか。頭全体を締めつけられるイメージです。

また、肩や首のキツイこり、めまいやふらつき、全身のだるさなどを伴うこともあります。子どもから高齢者まで、どの年齢層でもみられ、ときどき頭痛がするタイプ(反復性緊張型頭痛)と、毎日のように頭痛が続くタイプ(慢性緊張型頭痛)とがあります。
主におでこ、後頭部、側頭部、頭頂部、首筋にかけて起こりやすく、温めたりして緊張がとれると緩和するのも特徴です。
②偏頭痛
名前の漢字通り、片側に起こることが多い頭痛です。
「拍動性の頭痛」で、脈を打つような感じでズキンズキンと痛むことが特徴です。
頻度は月に1〜2度、多い人で週に1〜2回 頭を動かすと痛い、光や音、臭いに敏感になる吐き気がするなどの特徴があります。20代〜40代の女性に多くみられます、またアロディニアと呼ばれ眼鏡や髪を結んでいるのに不快感を感じる前兆がみられることもあります。前兆として、目の前にチカチカとしたフラッシュのような光やギザギザした光があらわれたり、視野の一部が見えにくくなる閃輝暗点(せんきあんてん)が出ることもある。
③群発性頭痛
1~2ヶ月の間に集中して(群発的に)ほぼ毎日起こります。
症状は必ず片側に起こり、目の奥をえぐられるような激痛、そして鼻水や涙、目の充血を伴うことがあります。
動くと少しマシだが、痛みでジッとしていられずたえがたい痛みが襲われます。季節の変わり目や就寝後、明け方におこりやすい。男女比は7:1と男性に多い(20代〜30代) 他の頭痛に比べ稀な頭痛です。
それぞれの頭痛の原因は?
さて、まずは一般的にいわれている原因の説明から
①緊張型頭痛
一般的には身体的・精神的なストレスによるものだと考えられています。
身体的ストレスとは、たとえば上体を前かがみにしてのデスクワークや、うつむいた姿勢、赤ちゃんを抱っこする姿勢
家庭内でのトラブルや仕事がうまくいかないなどの精神的ストレスも、神経や筋肉の緊張を高め、頭痛の誘因となります。 緊張型の頭痛と言われるだけあって、緊張を招くような要素が症状の原因であるとされています。

②偏頭痛
偏頭痛は頭の中で血管が広がり、拍動することで周囲の神経に刺激が伝わることにより起こります。
脳の太い血管が拡張すると、その周囲を取り巻いている頭の中で一番大きな神経「三叉神経」が圧迫され、刺激を受けます。刺激を受けた三叉神経からは神経ペプチドとよばれる「痛みの原因となる物質」が放出され、血管の周りに炎症が起こります。
するとさらに血管が拡張し、ますます周りの三叉神経が刺激されます。この刺激が大脳に伝わり、“痛み”として認識されることによって、頭痛が起こるのです。この三叉神経からの情報が大脳に伝わる途中で視覚や聴覚、嗅覚を司る中枢(後頭葉、側頭葉)や、吐き気をコントロールする嘔吐中枢にも刺激が伝わります。それによって、光や音、においに敏感になったり、吐き気や嘔吐といった随伴症状があらわれます。
また、血管が拡張する原因のひとつに「セロトニンの過剰な放出」が考えられています。過度のストレスにより脳が刺激を受けると、血液成分のひとつ「血小板」から血管を収縮させる作用をもつ「セロトニン」が大量に放出され、脳の血管が収縮します。その後、時間の経過とともにセロトニンが分解・排泄されて減少すると、収縮していた血管が今度は反動で急激に拡がり、頭痛が起こるというものです。
③群発性頭痛
群発性頭痛の発症の原因については、明らかにされていない点が多々ありますが、頭部の血管の拡張が関わっていると考えられています。群発性頭痛の場合は、目の後ろを通っている血管が拡張して炎症を引き起こすため、目の奥が痛むといわれています。
また、この血管を取り巻いている自律神経は、涙腺のはたらきや瞳孔の大きさをコントロールしているので、刺激されることで涙が出る、瞳孔が小さくなるといった症状を伴うこともあります。群発性頭痛ではアルコールが誘発因子になり、飲酒後40分から1時間ほどたった頃に発作があらわれやすいといわれています。群発期には、飲酒するとほぼ百発百中で頭痛が起きるため、どんなにお酒好きの人もその期間はアルコールを避けるようです。
それ以外にもタバコや気圧の急激な変化なども誘因となるといわれています。
いずれの頭痛も主に処方材を使うことがメインとなります。

呼吸からみた頭痛
「呼吸と頭痛?」
そう思った方もいらっしゃるかとは思いますが、ここで言う呼吸とは普段私たちがしている鼻や口から行っている呼吸とはまた別のものです。
まず、私たちの頭蓋骨は複数の骨がパズルのピースのように合わさることで一つの形を作っています。

そのひとつひとつの骨がそれぞれ固有の動きを行っており、それを「一次呼吸」と呼んでいます。(ちなみに、鼻や口からの呼吸のことは二次呼吸と言います)
この一次呼吸の働きが低下することで頭痛を巻き起こす可能性があるのです。
人の頭蓋骨の中は”脳脊髄液”という液で満たされており、その中に脳が浮かんでいる状態となります。
分かりやすく言うと、パック売りされている豆腐。

プラスチックの容器が頭蓋骨、中で豆腐を守っているお水が脳脊髄液で、豆腐そのものが脳だとすればイメージしやすいですね。
容器である頭蓋骨が一次呼吸を行うことで、脳脊髄液は産生されたり吸収されたりしながら循環していきます。
しかし、ここでこの循環サイクルが乱れたり、正常に機能しなくなった場合、今回のような頭痛を招くケースもあります。たとえば、脳脊髄液の吸収がうまくされない状態だったらどうでしょう。脳内に過剰に溜まった脳脊髄液のせいで脳圧はグッと上がってしまいます。脳圧が上がれば頭は重たくなり、痛み症状にもつながってきます。
そして、その一次呼吸を整えるのが得意なのが整体(頭蓋仙骨療法-クラニオセイクラル-と言われています)です。
精神的・身体的なストレスで体は緊張したり不調を招きますが、この一次呼吸を調整することで今までの頭痛がスッキリ良くなる可能性は十分にあります。
統合医療からみた頭痛
まずは統合医療のお話から。
もともと、疾病を施術し症状を緩和する方法には「対症療法」と「原因療法」があります。これまで多くの医療機関などで実践されてきた医療は、「対症療法」を中心とした近代西洋医学を根本としてきました。
しかし昨今、国際的な医療の動向は、単に病だけではなく、人間の心身全体を診る「原因療法」を中心とした伝統医学や相補・代替医療も必要であるという考え方に急速に移行しています。
統合医療とは、二つの療法を統合することによって両者の特性を最大限に活かし、一人ひとりの利用者に最も適切な『オーダーメイド医療』を提供しようとするものです。

そして、統合医療の第一線で活躍されているおのころ心平さんによると、頭痛の部位によって潜在的に何が影響しているのか、そしてどの臓器に負担がかかっているのかが分かるということです。
分類ごとに見ていきましょう。
頭痛(こめかみ)
☆潜在的なココロ:追い立てられることへの不安、性的な恐れ、流れに抵抗する
★関連臓器:肝臓
頭痛(首筋から後頭部にかけて)
☆潜在的なココロ:自己否定、自己批判、あるいは、これ以上は動けないという気持ち
★関連臓器:脾臓
頭痛(前頭部)
☆潜在的なココロ:前進への不安、前に進むのに抱えすぎている問題
★関連臓器:肺
頭重感を伴う頭痛
☆潜在的なココロ:背後への不安、周りの理解を得られるかの不安
★関連臓器:腎臓
偏頭痛
☆潜在的なココロ:いざという時、誰も助けてくれないのではないか、という不安
★関連臓器:心臓
一般的に聞かない心理が今回の頭痛にも含まれていることが分かります。
ちなみに、私は腎臓に負担をかけやすい体質なのですが、頭の症状が出るとなると必ず頭重感を伴います。
統合医療の観点、恐るべし。。。
東洋医学からみた頭痛
東洋医学の考え方のひとつとして、「実(じつ)と虚(きょ)」というものがあります。
以前、肩こりの解説をした際、熱が上に昇ると頭痛を引き起こす。
という記事を書きましたが、捉え方としてはそれに近いものがあります。
(その時の記事はコチラから)
↓ ↓ ↓
東洋医学からみた肩こり・頭痛~余分な熱が悪さをする!?~
”実”というのは、「体のエネルギーバランスが過剰になっている状態です」
イメージするならこんな感じ
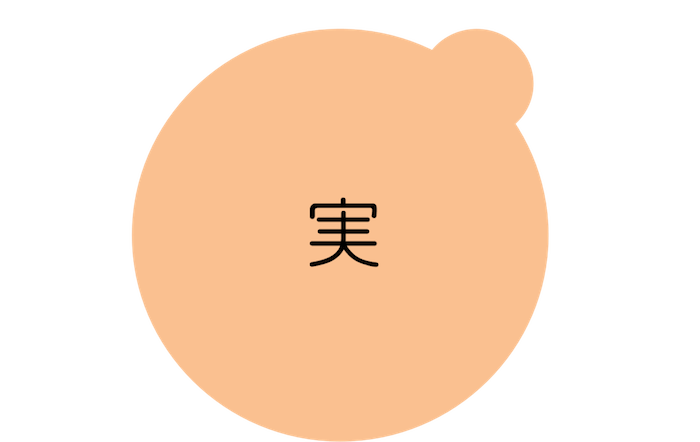
逆に、”虚”の状態というのは、「体のエネルギーバランスが不足している状態」
イメージ図↓
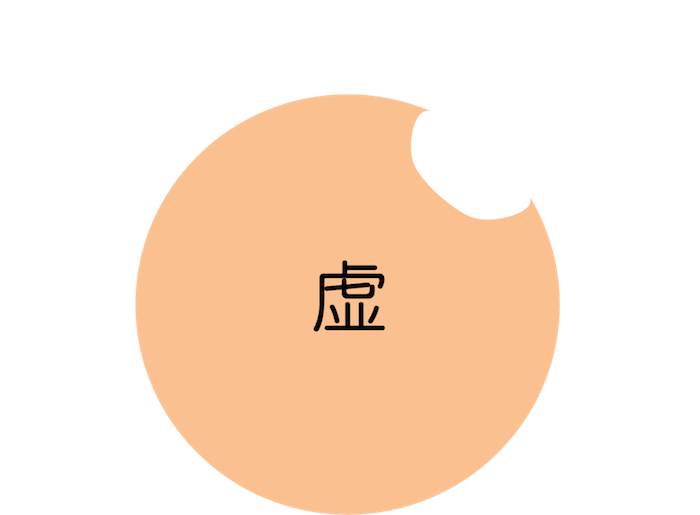
必要なエネルギーが不足して欠けていることが分かりますね。
このエネルギーバランスは、本来ならきれいな円形になっているのが健康であり望ましいです。
しかし、生活習慣や環境によってこのバランスは崩れ、症状が表面に出てくることとなります。
特に、デスクワーカーの方などは一日中座りっぱなしの状態ですよね。
冷気は下にいきますから、冬はもちろん夏でもクーラーで足元は冷えるし、その割には頭や目を使うので血液や「気」は上に集まってしまいます。
このように、エネルギーバランスが上に偏って下に巡っていない状態のことを「上実下虚(じょうじつかきょ)」と言います。
この状態が続くことで頭痛がひどくなる方は臨床上でも数多くいらっしゃいます。
整体太郎と鍼灸花子での頭痛のサポートとは?
先ほど、人の一次呼吸をパックのお豆腐に例えて解説しましたね。
まさにそのお水(脳脊髄液)の流れを調整するには整体が有効です。
頭蓋骨の調整やその他循環の妨げとなる箇所を施術することで、お悩みの頭痛から解放されるようにサポートいたします。
東洋医学の説明であったような「実と虚」の状態。
こちらを整えるためには、鍼灸療法が有効となります。
その方の虚実のバランスを検査し、ピッタリのツボ選び、そして頭痛を引き起こす発痛物質の排泄を促します。
【記事作成者 整体太郎と鍼灸花子(吹田市江坂)】